電子署名と電子証明書の違いとは?役割や仕組み、法的効力を分かりやすく解説
「電子署名」と「電子証明書」。この2つの違いをひと言で説明できますか? ずばり、その違いは「ハンコ(印鑑)」と「印鑑証明書」の関係と同じです。
こう聞くと、「なるほど」と思う反面、「では、なぜそれが電子契約に必要なのか?」「どうやって法的な効力を担保しているのか?」といった新たな疑問も湧いてくるかもしれません。
この記事では、電子契約の根幹となる電子署名と電子証明書の違いや役割、そして電子契約が法的に有効である理由を分かりやすく解説します。読み終える頃には、電子契約の仕組みへの不安が解消され、自社に導入すべき理由が明確になっているはずです。
電子署名と電子証明書の違い

電子署名と電子証明書はどちらも電子契約を支える仕組みですが、役割と目的が異なります。紙の契約で例えるなら、「電子署名」は印鑑そのもの、「電子証明書」はその印鑑が本物であることを示す印鑑証明書のような位置づけです。
電子署名は、ある文書を「確かにこの人が作成・承認した」という本人性と、「内容が改ざんされていない」という非改ざん性を保証するための仕組みです。契約書などの電子データに対して署名を行うことで、誰がその文書を作成・承認したのかを証明できます。
一方の電子証明書は、その電子署名を行った人や組織が本当に本人であるかどうかを第三者が証明するためのものです。公的な認証局が発行し、「この公開鍵は確かに〇〇社のものです」といった身元情報を保証します。これにより、署名がなりすましによるものではなく、正当なものであることが確認できるのです。
つまり、「電子署名」と「電子証明書」は片方だけでは成り立たず、両方がそろって初めて電子契約の信頼性が担保されます。印鑑と印鑑証明書の関係と同じように、それぞれが異なる役割を果たしながらも密接に結びついているのです。
次のセクションでは、この2つについてさらに詳しく掘り下げていきます。
そもそも電子署名とは

電子署名とは、紙の契約書で言うところの署名や押印の役割を電子データ上で果たすもので、誰が文書を承認したのかと、内容が変更されていないかを技術的に証明します。
本人性の証明
電子署名の基本的な役割のひとつが、この文書を承認したのは確かにこの人(この組織)であると証明することです。紙の契約書であれば署名や印鑑がその役割を担っていましたが、電子契約では暗号技術を用いてそれを実現します。
具体的には、署名者だけが持つ秘密鍵で署名を行い、受け取った側は対応する公開鍵でその署名を検証します。この検証が正しく行われれば、その文書は秘密鍵の持ち主=本人によって署名されたものと確認できる仕組みです。
この技術により、なりすましなどの不正行為を防ぎ、契約書や申請書といった重要な文書が本当に当人によるものとして信頼性を持てるようになります。
非改ざん性の証明
電子署名が果たすもうひとつの重要な役割が、署名後に文書が改ざんされていないことを証明することです。電子データはコピーや編集が容易なため、内容が途中で書き換えられていないと示せる仕組みが欠かせません。
電子署名では、文書の内容からハッシュ値と呼ばれるデータを生成し、それとともに署名します。もし一文字でも変更が加えられるとハッシュ値が一致しなくなり、署名が無効と判定されます。これにより、改ざんの有無が一目で確認できるのです。
この非改ざん性の仕組みによって、電子署名された文書は高い証拠力を持つデータとして扱えます。内容の正確性と信頼性が確保されることで、電子契約は紙の契約書と同等の法的効力を持つものとなります。
電子証明書とは

電子証明書とは、電子署名を行った人や組織が「本物である」ことを第三者が保証する、いわばデジタルな身分証明書です。
電子署名の持ち主を証明する身分証明書
電子署名が「誰が文書を承認したか」を示すものだとすれば、電子証明書はその「誰か」が本当に本人であることを証明する役割を担います。紙の契約でいえば、印鑑に対する印鑑証明書のような位置づけです。
電子証明書は、信頼できる第三者機関である「認証局(CA)」によって発行されます。認証局は、署名者の身元情報や公開鍵といった情報を審査し、それが確かに本人のものであると保証する存在です。
この仕組みにより、受け取った側は電子署名の背後にいる人物や組織が実在し、なりすましではないことを確認できます。電子契約における信頼の裏付けとして、電子証明書は欠かせない存在です。
電子証明書に含まれる情報
電子証明書が公的な身分証明書として機能するため、その内部には署名者の身元を特定し、署名を検証するための重要な情報が記録されています。普段は目にすることはありませんが、こうした情報があることで契約の安全性が支えられているのです。
記載されている主な内容には、署名した個人や企業・組織の名前、有効期限、証明書ごとに割り当てられた固有のシリアル番号などがあります。これによって、「誰が」「いつまで有効な証明書で」署名したのかが明確になります。
また、署名の正当性を検証するための技術的なデータや、証明書を発行した認証局の情報も記録されています。これらの情報がすべて揃うことで、電子署名の持ち主が正当であることが保証され、契約書全体の信頼性が担保されるのです。
発行方法
電子証明書は、前述した認証局へ申請手続きを行うことで発行されます。誰でも簡単に入手できるわけではなく、法人の場合は登記情報、個人の場合は公的な本人確認書類を提出するなど、厳格な審査を経て初めて手に入れることができます。
このような厳格な本人確認プロセスを経るからこそ、電子証明書は非常に高い信頼性を持つ身分証明書として機能します。手続きに手間と時間がかかるのは、その信頼性を担保するために他なりません。
しかし、契約のたびに企業や個人がこの複雑な発行手続きを行うのは、時間的にも費用的にも大きな負担となります。そのため、多くの電子契約サービスでは、利用者がこの手続きを意識することなく、簡単かつ安全に契約を締結できる仕組みを提供しているのです。
電子契約の法的効力は?電子署名法を解説
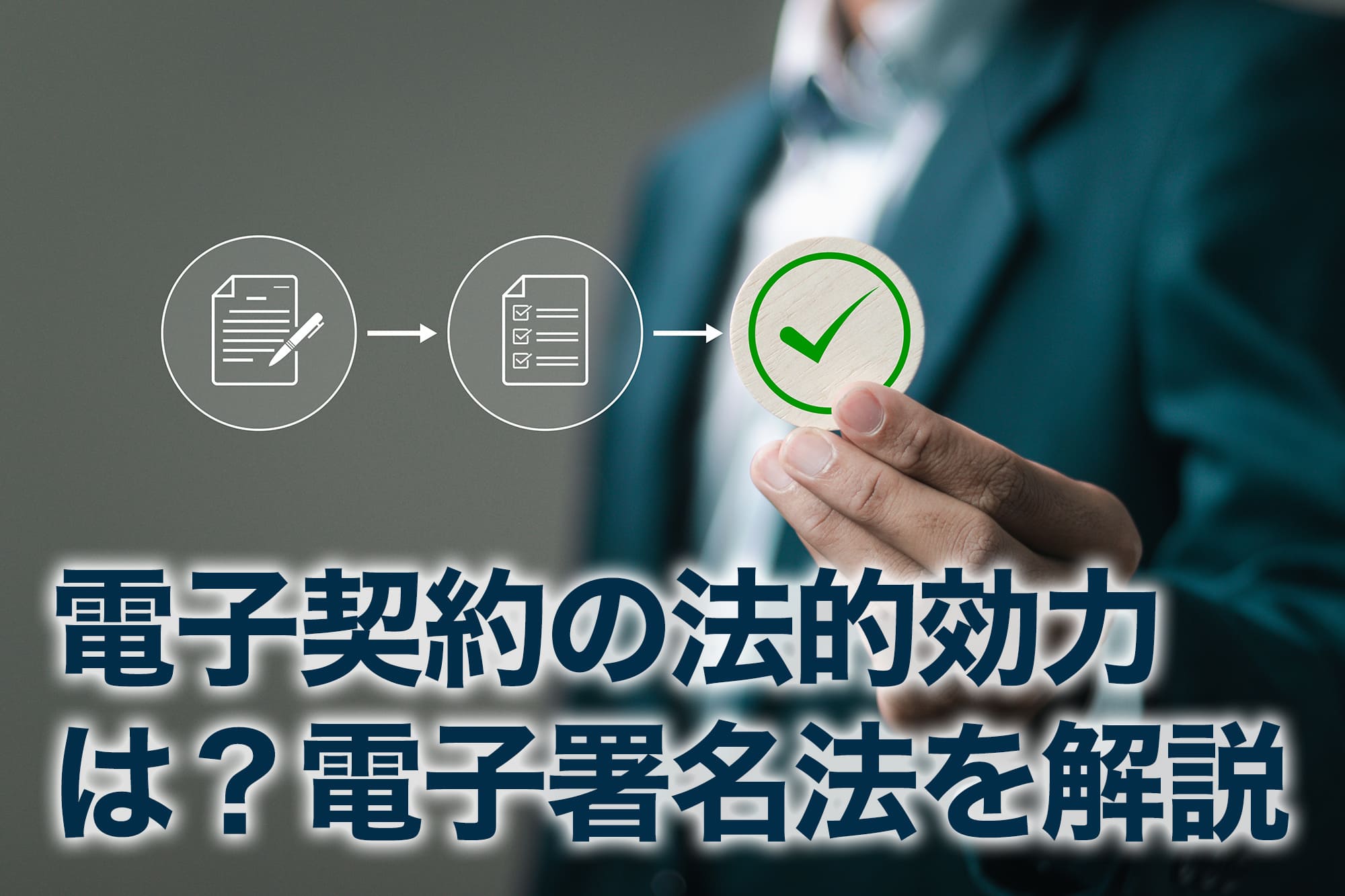
電子契約は、紙の契約書と同様に法的な効力を持つ契約手段です。その根拠となる「電子署名法」の仕組みと、契約の信頼性を支える2種類の電子署名について詳しく見ていきましょう。
電子契約の有効性
電子契約は、単なるデジタルなやり取りではなく、法律上も紙の契約書と同等の効力を持ちます。その根拠となるのが「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」です。この法律は、電子署名が付された電子文書に「本人による署名があった」と推定する効力を与えています。
つまり、電子署名法に基づいて正しく署名された契約書は、「本人がその内容に同意した」と見なされ、法的な証拠として通用します。紙の契約書で署名や押印がある場合と同様に、裁判などの場面でも証拠として提出できるのです。
ただし、電子署名が法的効力を持つには「本人によるものであること」「改ざんされていないこと」が確認できる必要があります。そのため、署名の仕組みや証明書の管理が適切であることが重要であり、信頼性の高い電子契約サービスを選ぶことが欠かせません。
電子契約の仕組みについては、関連記事も参照してみてください。
2種類の電子署名
電子署名法が定める電子署名には、その仕組みによって大きく2つの種類が存在します。これは、紙の契約でいえば「実印」と「認印」の使い分けに近いイメージです。
ひとつは「当事者型電子署名」です。これは署名する本人(当事者)が、認証局から直接電子証明書の交付を受け、厳格な本人確認のもとで署名する方式です。法的効力が非常に高い反面、発行に手間とコストがかかり、契約相手にも同様の準備を求める必要があるため、利用のハードルが高いのが実情といえます。
もうひとつが「立会人型(事業者署名型)電子署名」です。これは、契約当事者ではなく、電子契約サービスの提供事業者が立会人として電子署名を行う方式です。事業者がメール認証などで当事者の本人確認を行い、その締結プロセス全体を記録することで契約の証拠力を担保します。
現在、クラウド型の電子契約サービスの多くがこの立会人型を採用しており、「リーガルサイン」もこの方式によって、十分な法的効力を担保しながら、利用者にとっての利便性を実現しています。
なぜ電子契約サービスが必要なのか

電子契約サービスは、専門知識がなくても安全に契約を結べる環境を整え、紙契約に比べて大幅なコスト削減を実現します。また、電子署名法などの法的要件にも対応できます。
複雑な仕組みは不要
電子契約サービスを利用すれば、利用者は専門的な技術や法律をほとんど意識せずに済みます。
本来、電子署名やタイムスタンプの付与、電子証明書の管理には、暗号技術など専門的な知識が求められます。しかし、電子契約サービスを使えば、契約書ファイルをアップロードし、相手のメールアドレスを指定して送信するだけです。受け取った相手も、メールのリンクをクリックし、画面の指示に従って同意するだけで契約が完了します。
面倒で複雑な電子署名の付与や証明書との紐付け、法的に有効な状態での保管といった作業は、すべてサービスが裏側で自動的に行ってくれます。利用者は、普段使っているメールのような簡単な操作で、法的に有効な契約を結ぶことができるのです。
コストメリットがある
電子契約の導入は、紙の契約書にかかっていた印刷・製本・郵送のコストを削減できるだけでなく、印紙税が不要になるメリットもあります。紙の契約書では課税文書ごとに印紙を貼る必要がありますが、電子契約では印紙税の対象外とされているため、契約件数が多い企業ほど削減効果は大きくなります。
例えば、1契約あたり数百円〜数千円の印紙代が不要になることで、年間では数十万円単位のコストダウンにつながるケースも珍しくありません。これに加えて郵送費や人件費も抑えられるため、全体的な業務コストの圧縮効果が期待できます。
また、契約処理のスピードが上がることで取引の機会損失も減少します。コスト削減と業務効率化の両面から、電子契約サービスの導入は企業経営にとって大きなメリットをもたらすのです。
法的要件を遵守できる
電子契約を有効なものとして保管するには、先に説明した電子署名法だけでなく、電子帳簿保存法という法律の要件も満たす必要があります。この法律では、電子取引データの保存方法について、改ざん防止措置や検索機能の確保など、細かいルールが定められています。
合わせて読みたい:電子帳簿保存法を導入しない場合どうなる?コストゼロで始める最低限の対応策
自社でこれらの法的要件をすべて正確に把握し、対応し続けるのは非常に困難です。法改正が行われれば、その都度システムを改修する必要も出てくるでしょう。
その点、電子契約サービスは、電子帳簿保存法などの関連法規に準拠するように設計されています。サービスを利用するだけで、法的なリスクを心配することなく、安心して契約書をデータとして保管・管理できます。企業コンプライアンスの観点からも、専門のサービスに任せるのが賢明です。
簡単・安全な電子契約なら「リーガルサイン」がおすすめ
%E3%81%AE%E3%83%AD%E3%82%B4%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg?width=2000&height=1333&name=Legal%20Sign(%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3)%E3%81%AE%E3%83%AD%E3%82%B4%E7%94%BB%E5%83%8F.jpg)
電子契約サービスの導入を検討する際には、料金の分かりやすさ、機能の充実度、そして導入後のサポート体制が大きなポイントになります。
「リーガルサイン」は、この3つの条件を高い水準で満たしたサービスとして多くの企業に選ばれています。
利用しやすい料金
リーガルサインは、使用頻度に応じてプランを選べるシンプルな料金体系を採用しています。機能制限や追加オプション費用といった煩雑な仕組みがなく、月額料金だけで利用できるため予算管理もしやすいのが特徴です。
また、初期費用や違約金、契約期間の縛りが一切ないため、導入のハードルが低く、スモールスタートにも適しています。結果として、紙の契約書で発生していた印紙税や郵送費用を含め、大幅なコスト削減につながります。
月額料金内で全機能を利用可能
電子契約に必要な機能はすべて月額料金に含まれており、追加料金を気にせず使えるのも安心できるポイントです。クラウド上での契約締結やタイムスタンプ、デジタル印鑑の作成、複数人が関与する契約への対応など、業務に直結する機能が網羅されています。
契約書の有効期限設定や合意締結証明書の自動発行、リマインドメール送信など、実務の効率化を支える機能も標準搭載されています。PDFアップロードや電子署名、契約書の保管・検索といった基本機能はもちろん、EメールやSMSによる署名依頼もでき、契約相手に応じた柔軟な対応が可能です。
万全のサポート
導入後すぐに利用できるよう、初日から全面的なサポートを提供しているのもリーガルサインの魅力です。利用者が管理者であっても従業員であっても、誰でもサポート窓口を利用できる仕組みが整っており、新入社員向けの研修や支社からの問い合わせにも丁寧に対応しています。
サポートは利用期間中であればいつでも何度でも無料で受けられるため、安心して業務に組み込めます。ビデオ通話やオンライン予約システム「TimeRex」を活用した相談も可能で、スピーディーかつ柔軟な対応が期待できます。導入前の不安を解消し、運用後も長期的に伴走してくれる体制は、多忙な現場にとって大きな安心材料となるでしょう。
まとめ
電子署名と電子証明書は、それぞれが異なる役割を担いながら、電子契約の信頼性と法的効力を支える重要な仕組みです。電子契約を導入することで、紙の契約書にかかっていた手間やコスト、印紙税の負担を減らし、業務全体の効率化にもつながります。
こうした電子契約をより手軽に、安全な形で導入したいときは、「リーガルサイン」のようなサービスを活用するのもひとつの方法です。導入をお考えなら、お気軽にお問い合わせください。

